なぜドラマ『HERO』は、放送から長い時間が経った今も「名作」と呼ばれ続けているのでしょうか。 派手なアクションがあるわけでも、毎話どんでん返しが用意されているわけでもありません。 それでも多くの人の記憶に残り、繰り返し語られる理由は、この作品が描いた「正義のかたち」にあります。
『HERO』が提示した正義は、単純な勧善懲悪ではありません。 犯人を早く捕まえること、事件を効率よく終わらせること、それ自体が正義なのか。 作品は一貫して、「本当にそれで納得できるのか?」と視聴者に問いかけ続けます。
主人公・久利生公平は、型破りな検事として描かれます。 ジーンズ姿で現場に足を運び、些細な違和感を見逃さず、事件の大小に関係なく真実を疑い続ける。 その姿は、正義を振りかざすヒーローというより、不器用なくらい真面目な一人の人間です。
本記事では、『HERO』がなぜ平成司法ドラマの到達点とまで言われるのかを、 「真実を疑う正義」という視点から丁寧に読み解いていきます。 現実の司法制度との距離感、城西支部という組織の描かれ方、 そして久利生公平という人物が私たちに残したものとは何だったのか。
懐かしさだけで終わらせず、今だからこそ見えてくる『HERO』の本質を、 一緒に振り返っていきましょう。
第1章|型破りな検事・久利生公平が壊した「検事像」
『HERO』が最初に視聴者へ突きつけるのは、「検事とはどうあるべきか」という固定観念を揺さぶる姿です。
従来のドラマに出てくる検事は、机の上の書類と向き合い、警察から送られてきた情報を整理し、淡々と起訴・不起訴を判断する“静”の存在でした。
画像をクリックするとAmazon商品ページへ飛びます。
しかし久利生公平は、そのイメージを根本から覆します。
ジーンズ姿で現場に向かい、些細な矛盾を見逃さず、気になることがあれば何度でも足を運ぶ。彼の行動力は時に「おでかけ検事」と揶揄され、城西支部の同僚たちからは呆れられるほどです。
ここで重要なのは、久利生が「型破り」なのではなく、本来の検事の役割を極めて真っ当な形で遂行しているという点です。
本来、検察官は独任制の官庁であり、証拠の評価も処分の決定もすべて自分の責任。だからこそ、机上の情報だけで判断するのではなく、自分の目と足で確かめる行為は、実は極めて合理的なのです。
とはいえ、実務の世界では膨大な案件を限られた人員で抱えており、同じような捜査スタイルを取るのは現実的ではありません。そのギャップこそが、久利生というキャラクターを“異端”に見せ、同時に彼の行動原理を際立たせます。
そしてもうひとつ、大切なポイントがあります。彼は事件の大小を問わず、「納得いくまで調べる」という姿勢を決して崩しません。
スルメ泥棒、下着泥棒……一見“軽微”とされる案件であっても、久利生にとってはすべてが等しく重要な事件です。ここに、後の章で語る「真実を疑う正義」が強く根付いています。
第2章|“真実を疑う”という正義の再定義
『HERO』が他の司法ドラマと決定的に違うのは、「真実は最初からそこにあるものではない」という前提を、徹底して描いている点です。
久利生公平は、警察から送られた書類を読んだだけで結論を出すことを良しとしません。むしろ、その中にある“違和感”を見つけることから捜査を始めます。
例えば、被疑者の供述と現場の状況がわずかに食い違っている。
あるいは、第三者の証言が「数字では説明できない何か」を含んでいる。
そうした小さな矛盾にこそ、真実へ続く鍵が隠れているのだと、久利生は知っています。
ここで重要なのが、彼は決して「人を疑うため」に矛盾を探しているのではなく、「自分の判断そのものを疑うため」に現場へ足を運ぶという点です。
効率や慣習に流されず、“自分が納得できるかどうか”を判断基準にしている姿勢こそ、『HERO』が提示した新しい正義のかたちです。
また、作品の中ではたびたび「その事件、そこまでやる必要ある?」という声が上がります。
しかし久利生は、事件の大小によって態度を変えることはしません。軽微とされる案件こそ、見落としが起きやすい。だからこそ、真実を丁寧に扱う。
この姿勢は、効率重視の組織文化とたびたび衝突しますが、視聴者にとっては強い説得力を持って映ります。
そして何より、『HERO』の物語は視聴者にこう問いかけます。
「あなたは、本当にその“真実”を信じていいのか?」
この疑問が、ドラマ全体を貫く強力なテーマとして機能しているのです。
HERO Blu-ray BOX
HERO Blu-ray BOX
✅ Amazonでチェックする
✅ 楽天でチェックする
第3章|現実の司法制度と『HERO』の距離感
『HERO』が特異なドラマである理由のひとつに、「現実の司法制度」との絶妙な距離感があります。
検察官は日本の刑事手続において強大な権限を持ち、起訴・不起訴を唯一決定できる存在です。つまり、彼らの判断ひとつで人生が大きく変わる可能性があります。
しかし実務の現場では、ほとんどの検事が膨大な案件を抱え、書類から事実を組み立てる作業に追われています。
自ら積極的に現場へ向かうのは、重大事件など限られたケースが中心で、久利生公平のように毎日のように外へ出て調べ回るスタイルは、現実にはかなり珍しいものです。
ではなぜ、視聴者はその違和感を気にせず物語に没頭できるのでしょうか。
その理由は、ドラマが司法の“形式的なリアリティ”より、「真実と向き合うための姿勢」という“本質的なリアリティ”を優先して描いているからです。
久利生の行動原理は一貫しています。
「書類はただの記録であって、真実ではない」という考え方。
彼は、証言や供述の裏側にある“空気”や“温度”のような定量化できない情報を拾い集め、そこから事件の輪郭を立体的に捉えようとします。
この視点は、現実の司法制度ではなかなか描かれない部分です。
しかし、だからこそ視聴者は「もし検事が本当にここまで向き合ってくれたら」と想像し、物語に強い説得力を感じます。

『HERO』は、制度の限界と理想の狭間にある“リアルな正義”を描いた作品でもあるのです。
第4章|城西支部という「組織」の物語
『HERO』の魅力は、久利生公平という個人だけで成り立っているわけではありません。
物語の舞台である東京地検・城西支部の存在こそ、作品全体の厚みを生み出す重要な要素です。
城西支部には、出世を重んじる検事、前例主義に従う事務官、保身に走りがちな管理職など、いかにも“組織”らしい人々が揃っています。彼らは決して悪人ではありませんが、膨大な案件を処理する毎日の中で、いつのまにか「効率」や「組織の論理」を優先するようになってしまった人たちです。
そんな中に放り込まれるのが、久利生という異端の存在。
ある事件に違和感を覚えれば、書類が整っていても「これ、ほんとにそうですか?」と平然とぶつけてしまう。組織にとっては非常に扱いづらい人物です。
しかし物語が進むにつれ、城西支部のメンバーは、久利生の行動原理に少しずつ触発されていきます。
最初は呆れていた同僚が、いつの間にか彼の捜査に同行し、結果として事件の真相に近づくことも少なくありません。
特に、事務官の雨宮舞子や麻木千佳との関係性は象徴的です。
最初は手を焼くばかりだった久利生の“おでかけ”に付き合ううちに、彼女たちの中にも「真実に向き合うとはどういうことか」という感覚が芽生えていきます。
この変化が、単なる「事件解決ドラマ」ではなく、価値観が変わっていく群像劇としての『HERO』の魅力を高めています。
城西支部のメンバーは、久利生と対立するための“壁”として登場するのではなく、彼の存在を通して少しずつ変化していく“鏡”として描かれています。

この構造があるからこそ、視聴者は「正義とは、誰かひとりのものではない」というメッセージを自然と受け取るのです。
第5章|ガジェットと日常性が生んだリアリティ
『HERO』はシリアスな司法ドラマでありながら、どこか生活感のある世界観が魅力のひとつです。
久利生公平という人物を“普通の人間”として感じさせるために、作品はガジェットや日常描写を巧みに使っています。
象徴的なのが、検事バッジである秋霜烈日章の扱い。
通常はスーツの襟元につけるものですが、久利生はジーンズのポケットやネックレスにぶら下げるなど、まったく権威に寄りかからない持ち方をします。
この描写は、彼の「権力よりも真実」というスタンスをわかりやすく象徴しています。
また、彼が愛用する通販グッズの数々や、行きつけのバー「St.George’s Tavern」、
さらにはA BATHING APEのダウンなど、当時の空気感を伝えるアイテムが随所に登場します。
こうした細部のこだわりこそ、ドラマの世界観にリアリティを与え、視聴者の“没入感”を支えています。
日常の延長線上にある人物が、ひたむきに真実と向き合うからこそ、久利生の行動はより強く心に響くのです。

「特別な人間」ではなく、「どこにでもいるけれど、誰よりも誠実な人」として描かれている点こそ、視聴者が久利生に親近感を覚える大きな理由と言えるでしょう。
HERO(プライムビデオ)
HERO プライムビデオ
✅ Amazonでチェックする
第6章|なぜ『HERO』は時代を超えた名作なのか
ここまで見てきたように、『HERO』は単なる刑事・司法ドラマにとどまりません。
事件を解決する過程だけでなく、「正義とは何か」「真実とは何か」というテーマを、視聴者に静かに問い続ける作品です。
では、なぜ20年以上経った今でも“名作”として語られ続けているのでしょうか。
その理由のひとつは、物語の構造が勧善懲悪に依存していない点にあります。
誰かが悪者で、誰かが正義の味方…という単純な対立ではなく、
「みんながそれぞれ正しいと思っている世界」を前提に、物語が動いていきます。
久利生公平が向き合うのは、犯人ではありません。
“自分が信じようとしている真実、そのもの”です。
彼は最初から相手を疑っているのではなく、自分の判断を疑っているからこそ、足を使って事実を確かめに行きます。
こうした「姿勢としての正義」は、時代が変わっても色褪せません。
むしろ、情報があふれ、結論が急がれる現代では、
“ゆっくり確認して、納得したうえで判断する”というスタンスはより価値を増しています。
さらに、『HERO』が愛され続けるもうひとつの理由は、キャラクターの関係性が普遍的に魅力的であること。
久利生と事務官との掛け合い、城西支部の人々の温度差、時折みせる人間臭さ…。
重いテーマを扱いながらも、肩の力を抜いて観られるバランス感覚が見事です。

事件の真相を追うスリルと、日常の温かみ。そして、揺るがない正義感。
これらが絶妙に組み合わさることで、『HERO』は単なるドラマの枠を超え、“人生のどこかで必ず思い出す作品”になったのだと言えるでしょう。
まとめ|『HERO』が教えてくれた「完成しない正義」
『HERO』は、司法の世界を舞台にしながら、単なる事件解決ドラマを超えた作品です。
描かれているのは、“正義とは何か”という抽象的な問いではなく、「どうやって真実と向き合うか」という、とても人間的な姿勢です。
久利生公平は、権威にも慣習にも頼らず、
「自分が納得できるかどうか」だけを軸に行動します。
事件の大小を問わず、書類だけで判断せず、必ず現場へ足を運び、わずかな違和感を大切にする。
その姿勢は、視聴者に“正義の形”よりも“正義の作り方”を教えてくれます。
『HERO』の物語は、巨大なパズルの最後の1ピースを探すようなもの。
どれだけ急いで完成させようとしても、そのピースが間違っていれば、絵は美しくならない。
だからこそ久利生は、時間がかかっても「自分の目で確かめる」ことをやめません。
そして、この姿勢こそが、多くの視聴者の心に残った理由です。
正義は完成された形で存在するのではなく、ひとつひとつ確かめながら積み重ねていくもの。
この普遍的なメッセージが、時代を超えて評価され続ける最大の理由と言えるでしょう。
『HERO』をもう一度見直すと、当時は気づかなかった“細部の意味”や“キャラクターの変化”が新しく見えてきます。
ぜひ、あの名作を改めて味わってみてください。
あわせて読みたい
参考文献
よくある質問
- Q久利生公平はなぜ事件の大小に関係なく徹底的に調べるの?
- A
彼にとって「小さな事件」など存在しないからです。
どんな案件でも、そこに当事者がおり、真実があります。
事件の規模に左右されず、ひとつひとつ丁寧に向き合う姿勢こそ、彼の正義そのものです。
- Q『HERO』の検事像は実際の検察官とどれくらい違う?
- A
現実の検察官は圧倒的にデスクワークが多く、久利生のように頻繁に現場へ行くケースは例外的です。
ただし、真実の追求という本質的な姿勢は、検察の根幹にある役割とも一致しています。
- Q今の時代に観ても古く感じない理由は?
- A
作品の中心にあるテーマが“人としてどう向き合うか”という普遍的なものだからです。
効率化や即断が求められる現代において、“疑い、確かめ、納得する”という姿勢はむしろ新鮮に映ります。

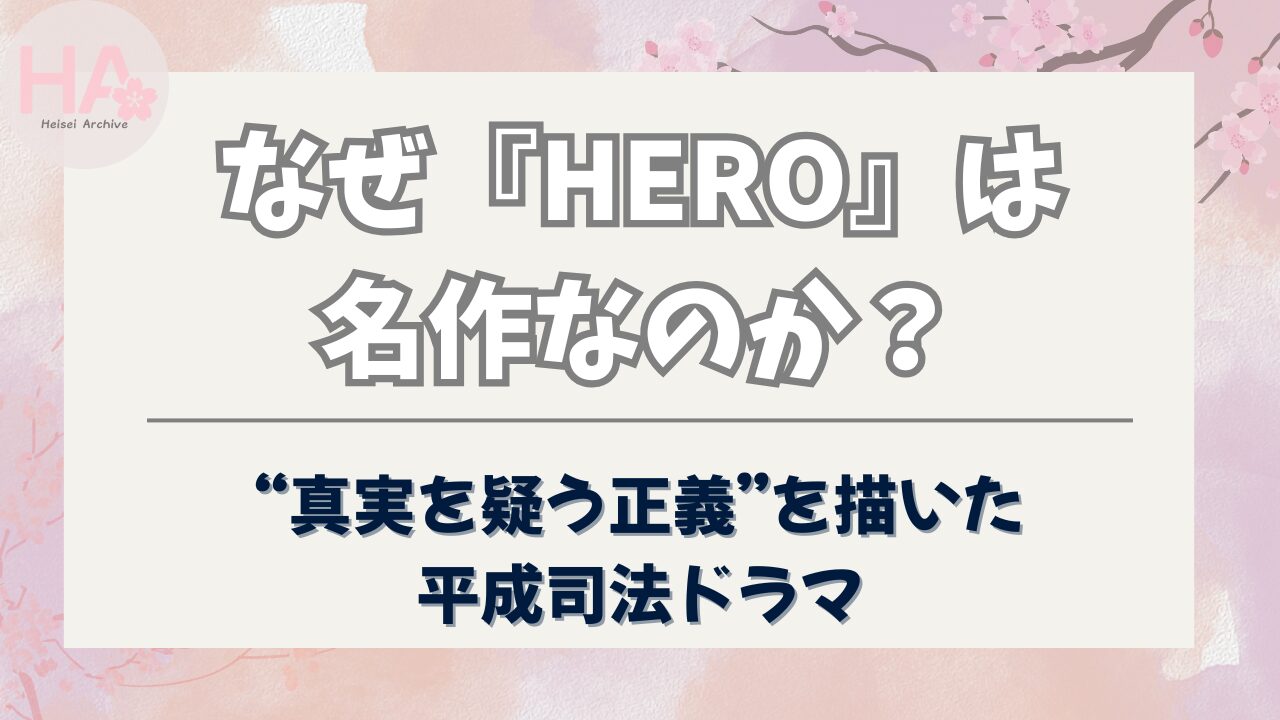


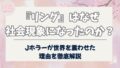

※当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。リンクを経由して商品を購入された場合、当サイトに報酬が発生することがあります。
※本記事に記載しているAmazon商品情報(価格、在庫状況、割引、配送条件など)は、執筆時点のAmazon.co.jp上の情報に基づいています。
最新の価格・在庫・配送条件などの詳細は、Amazonの商品ページをご確認ください。